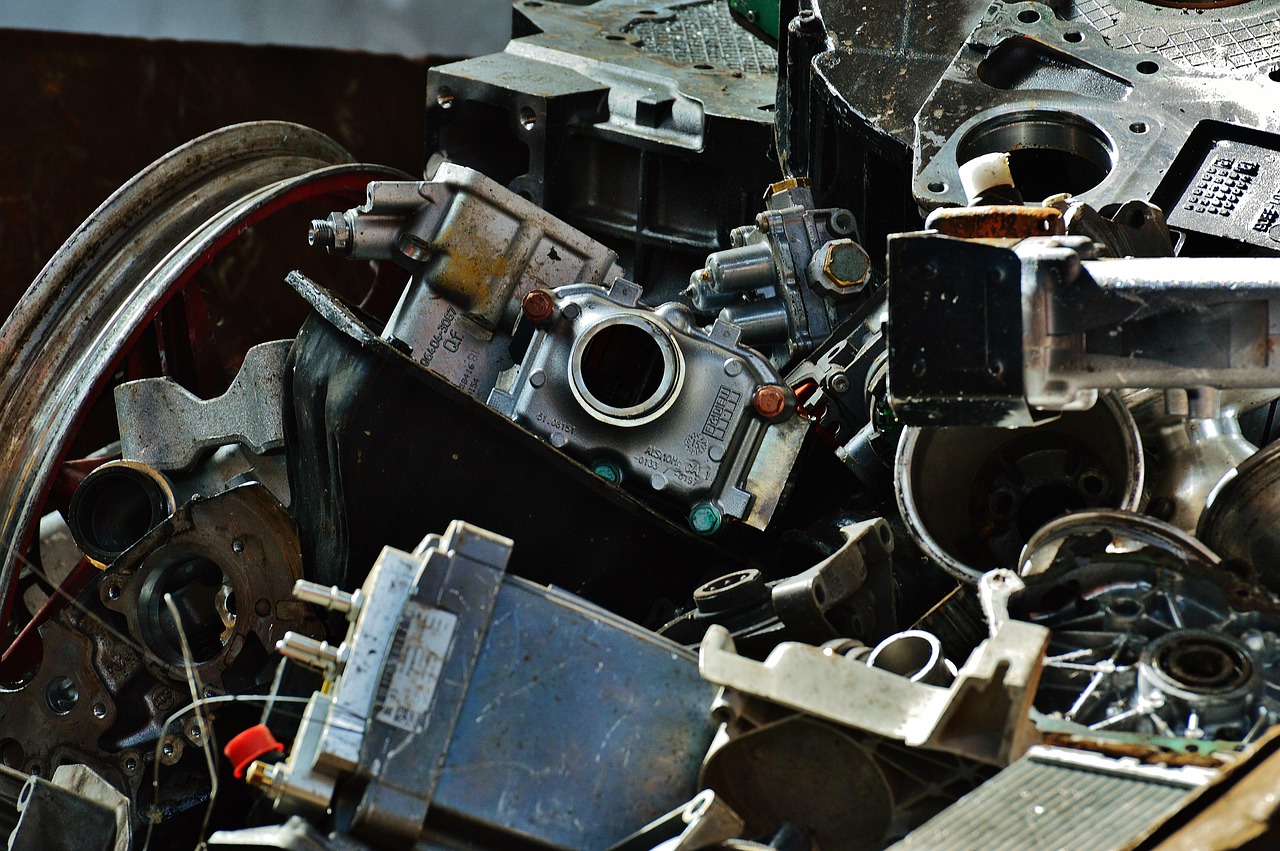ステンレスは錆びにくく、丈夫で清潔感があることから「キッチンのシンク、カトラリー、エレベーターの内装、建築部材、自転車の部品など」さまざまな分野で重宝されています。
「ステンレスは錆びない」というのが一般的なイメージですが、実際には「ステンレスなのに錆びてしまった」というトラブルは少なくありません。
この記事では、ステンレスの性質と「錆びる理由」錆びを防ぐ方法についてわかりやすく解説します。
ステンレスとは何か?
「ステンレス(Stainless)」とは、「錆びにくい(stain-less)」という意味の言葉で、「ステンレス鋼(stainless steel)」の略です。
これは鉄を主成分としながらも、クロムという金属を10.5%以上添加することで、表面に**不動態皮膜(ふどうたいひまく)という薄い酸化被膜を形成し、錆から内部の金属を守る仕組みを持っています。
この不動態皮膜が、ステンレスの「錆びにくさ」のカギです。傷がついても空気中の酸素や水と反応してすぐに皮膜が再生成され、自己修復的に防錆性能を保つという特徴があります。

それでも「錆びる」ステンレスの現実
ステンレスは「錆びにくい」金属ですが、「絶対に錆びない」わけではありません。錆びる条件がそろえば、やはり錆びてしまうのです。
錆びる原因を詳しく解説します。
1. 不動態皮膜が破壊される
ステンレスの表面を守る不動態皮膜も、強い酸や塩分、あるいは機械的な摩耗によって破壊されることがあります。
特に海沿いの地域や塩害が発生する場所では、空気中の塩分が皮膜を侵食し、錆びが発生しやすくなります。
2. もらい錆(接触腐食)
異なる金属(たとえば鉄やアルミなど)と接触することで、錆がステンレス側に「移る」ことがあります。
これを「もらい錆」と言います。たとえば、ステンレス製の流しに鉄製のたわしを置いたままにしておくと、たわしから出た錆がステンレスに付着し、そこから腐食が始まることがあります。
3. 汚れや水分の停滞
ステンレス表面に水分や油、汚れが長時間停滞すると、不動態皮膜の再生が妨げられ、腐食が進みやすくなります。
特に屋外に設置されたステンレス部材は、雨水やホコリの影響を受けやすく、定期的な清掃が必要です。
4. 適材適所ではない素材選定
ステンレスにも多くの種類があり、用途によって最適な種類を選ぶ必要があります。
「SUS304」は汎用的で錆びにくいとされていますが、塩分の多い環境では「SUS316」の方がより耐食性に優れています。安価なステンレスを選んでしまうと、結果的に錆びやすくなる場合もあります。
錆を防ぐためにできること
ステンレス製品を長持ちさせるには、いくつかのポイントを押さえることが大切です。
1. 定期的な清掃
ステンレスの表面に汚れや塩分が残っていると、腐食の原因になります。
中性洗剤を使ってやさしく洗い、水分を拭き取ることで、錆の発生を予防が可能。
特にキッチンや浴室など水気が多い場所では、こまめな清掃が効果的です。
2. 他金属との接触を避ける
鉄製品や異種金属との接触は避けましょう。
どうしても異種金属と接触させる必要がある場合は、間に絶縁材を挟むなどの工夫が求められます。
3. 使用環境に合ったステンレスを選ぶ
前述したように、使用する環境に応じて適切なステンレスの種類を選ぶことが大切です。例えば、食品工場や海辺の設備では、耐食性に優れたSUS316が推奨されます。
4. 表面処理やコーティング
必要に応じてステンレスの表面にコーティング処理(電解研磨やパッシベーション処理など)を施すことで、さらなる耐食性を付加できます。
【まとめ】錆びるステンレスは欠陥ではない
ステンレスは確かに「錆びにくい」金属ですが、「錆びない」金属ではありません。
不動態皮膜という優れた自己修復機能を持っている一方で、それを妨げる環境下では腐食が進行してしまいます。
「ステンレスなのに錆びた!」という経験をしないためにも、素材に対する正しい理解と、環境に応じた使い方・メンテナンスを心がけることが大切です。
日常の中で何気なく使っているステンレス製品。その輝きと強さは、実は私たちのちょっとした気配りによって保たれているのです。